第九話 碧海の彼方(6)
こうして、それぞれの場所で、様々な思惑が蠢く中、対するスペイン側はいかなる様相を呈していたであろうか。
その夜、スペイン軍総指揮官アレッチェは、指令本部を置いているリマのインディアス枢機会議本部の官邸を離れ、軍港を見下ろす沿岸に陣を張るスペイン軍大本営にいた。
トゥパク・アマルがそうであるのと同様に、このアレッチェもまた、目を配らねばならぬ場所が多々あった。
英国艦隊の到来が目前に迫った今、海戦に向けての準備は当然ながら、沿岸部における臨戦態勢の整備、そして、必ずやインカ側が奪還を狙ってくるであろうクスコへの監視も怠ることはできない。
その上、英国艦隊襲来の混乱に乗じて、国中に散らばるトゥパク・アマルの同盟軍や残党たちが、一斉に蜂起してくるであろうことも目に見えていた。
インカ軍に比して火器の面では圧倒的に勝るスペイン軍とて、その武力が無尽蔵にあるわけではない。
その限られた武力の采配に、さすがのアレッチェも頭が痛かった。

夜も更けた天幕の中で一人、アレッチェは、険しい表情でせわしなく書類を繰っている。
(英国艦隊の指揮官ジョンストンが率いる軍団は、提督直属の二戦艦だけでも、その搭載砲は114門……。
それに伴うパリアが率いる四戦艦の大砲を加えれば――艦砲の総数は、200門をくだらぬかもしれぬ)
彼の強靭な指先が、苛立たしげに葉巻を灰皿に擦り付けた。
そして、彫りの深い横顔では、冷徹な黒い瞳が宙を睨み据える。
己自身が火器にものを言わせてきただけに、アレッチェには、英国艦隊が自軍にもたらすであろう甚大な被害を、非常に生々しく、具体的に、想定することができた。
その脅威を思えば、今まで散々に手を焼かされてきたにもかかわらず、まともな火器を持たぬインカ軍など、赤子同然にさえ思えてくる。
だが、その錯覚を、彼は素早く振り払った。
天幕の外では海から吹きつける風が強まり、地を這うような低い雷鳴が夜の虚空を震わせている。
隙間風に揺れる燭台の炎が、憎悪に歪んだアレッチェの横顔を、闇の中に不気味に浮き上がらせた。
(今頃、インカ軍の本陣には、トゥパク・アマルが華々しく返り咲いていることだろう。
赤子の集団を、凶暴で狂信的な暴徒に変えるあの男が――!)
アレッチェは昂(たか)ぶった己の心を落ち着けるかのように、葉巻に火をつけると、その幅広い強靭な双肩を上下させながら、胃の腑まで深く煙を吸い込んだ。
それから、葉巻をくわえたまま、鋭利な面差しで再び書類を繰りはじめる。
それは、今しがた届けられたばかりの急送文書であった。
その重要な報告書によると、ペルー沖へ向かっている此度の英国艦隊に対して、数日前、同じ新大陸の他の植民地からスペイン本国へ帰還途上の航海中にあったスペイン艦が、激しい撃退を試みた。
しかし、結果は、あえなくスペイン側の敗退――。
結局は、英国艦とスペイン艦の力の差を、まざまざと見せつけられただけだった。
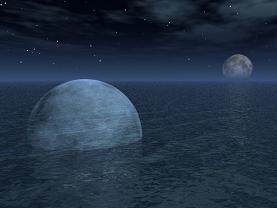
その苦々しい報告書に目を通しながら、しかし、アレッチェの冷徹で思慮深い眼差しには、決して失望のみではない色が宿っている。
(確かに、情けない結果ではあるが、ベネズエラやパナマ辺りから帰還途上であったスペイン艦など、概(おおむ)ね、苔むした使い物にならん老朽艦ばかりだ。
よほど有能な指揮官でもいない限り、あのジョンストンが率いる精鋭の英国艦と渡り合って、勝てるはずなどあるまい。
それよりも、その戦闘のおかげで、英国艦隊が当地に襲来するまでの時間稼ぎができた上に、幾らかでも英国艦に砲弾の消耗をさせることができたことが、ありがたい)
いつしか、天幕の外では、夜明けを告げる海鳥の声が、けたたましく響きはじめている。
アレッチェは立ち上がると、天幕入り口の垂れ布を荒々しく開け放った。
海岸線に沿った切り立った断崖上に布陣しているだけあって、天幕の正面には、白みを帯びた広大な水平線が遥々と見渡せる。
この瞬間にも英国艦隊が確実に迫り来ていることも、やがて炎の海となろうことも、まだ何も知らぬ、静かにまどろむ夜明けの海原――。
彼は、その視線をゆっくりと眼下の軍港へと動かしていく。
軍港の沖合では、昼夜を問わず、外敵の入港を封鎖するための戦列艦が、既に十隻近く遊弋(ゆうよく)しており、その間を、通信のための通報艦が、幾筋もの光る軌跡を描きながら慌しく駆け回っている。

アレッチェは昇りくる朝日に目を細めながら、それらのスペイン艦隊を眺めやった。
さすがに、外敵に狙われ続けてきたこのペルーに派遣されているスペイン艦は、他の植民地諸国に派遣されている老朽艦と比べれば、それなりに機能性と威力とを持ち合わせた艦が取り揃えられている。
特に、スペイン艦隊を総指揮する旗艦は、かつてコロンブスも出航したスペインのカディス港から、一昨年、当地に派遣されたばかりの精鋭の軍艦であった。
とはいえ、スペインにおいて海軍力の衰えの目立つこの時代、いかに精鋭の軍艦とはいえ、数十年前に建造された旧式の艦である。
確かに、スペイン艦にしては珍しく、それなりに能率を感じさせる外観をしてはいたが、かの力感あるスマートな美観と機能性を誇る英国艦に比して、このスペイン艦は重厚というか、いかにもずんぐりと重々しく、時代錯誤の感を否めない。
その上、艦尾やキャビン窓の周りには入念な彫刻とひどく派手派手しい黄金の装飾が施されており、アレッチェの目には、それらは全く無用の長物にしか見えなかった。
(いかにも一時代前の艦であることを、自ら物語っているも同然だ)
苛立たしげに睨み据えるアレッチェの視界の中で、その旗艦は高々と聳(そび)えるマストに褐色の帆を次々と広げはじめた。
帆に描かれた、スペイン艦を象徴する深紅の巨大な十字架が、目に痛いほど鮮烈に海原に映えている。
早朝の万帆の風を受けながら沖合へと進み行く旗艦に、周囲に遊弋していた数隻の戦列艦が、同様に帆を上げて付き従っていく。
周辺海域の監視と共に、英国艦隊との戦闘に備え、洋上で日々繰り返されてきた砲撃訓練へと今日も出帆していくスペイン艦隊――。
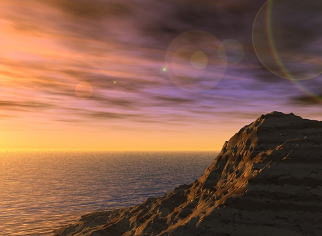
次第に水平線の方へと離れ行く、それら褐色の帆のピラミッド群を見つめながら、アレッチェはガッシリとした肩を聳やかせた。
(あれらの艦に頼るには限界も感じるが、しかし、艦の真の力を引き出すのは、艦の性能以上に、人間の側の能力と采配だ。
ならば、我らにも勝機はあろう。
そして、あとは、いかに「陸」を味方にできるかだ――)
かくして、沿岸の断崖上からアレッチェが視線を投げていたことなど知る由もないスペイン艦隊は、陸から離れると、まだ見ぬ英国海軍の仮想の艦影を洋上に描き出しながら、その日の激しい砲撃訓練を開始した。
実のところ、旗艦以外の艦船の乗組員たちは、本国スペインから当地に着任して以来、実戦経験からは長く遠ざかっていた。
外洋では、互いの植民地からの収奪物を巡る小競り合いは後を絶たなかったものの、このペルー沿岸まで攻め込まれるほどの戦闘には、この数年、幸いにも見舞われてはいなかったのだ。
もちろん、こうした事態の起こり得る可能性に備えて派遣されているのだが、まさか己らの任期中に、このような形で青天の霹靂のごとく現実として突きつけられようとは――彼らの心の奥底は、今も戸惑いに溢れ返っていた。
そして、その心境は、この旗艦の乗組員たちにおいても、そう大差はなかった。
今、艦の左右の舷側沿いにズラリと据えられた大砲の旋回から装填(そうてん)、照準、そして、砲撃まで、それら一連の動作を繰り返しながらも、その繰り出される砲弾は不安定で、彼らの動揺のさまが見て取れる。
そのような心もとない砲撃訓練の様相を後甲板から見下ろす艦長――ベルナルド艦長――もまた、あからさまに表に出すことは無いにしろ、その面持ちには、乗組員たちと同様に隠し切れぬ動揺の陰が覗く。

そして、その同じ旗艦上では、そのような砲撃訓練のさまを、険しくも思慮深い表情で見守るフロレスの姿があった。
訓練を指揮する海尉たちのがなり声に晒されながら、はやくも照りつけはじめた陽光の下で、汗だくの上半身をはだけ、半ズボンに裸足姿で甲板を慌しく走り回っている水兵たち――。
そんな男たちとは別世界にいるかのように、フロレスは、日に透ける肩ほどのブロンドを風に吹き流しながら、長剣を帯びた隙無い陸軍の軍服姿に身を包み、甲板を見晴らす艦首楼に立っている。
(見てくれも重々しい艦だが、繰り出される砲撃までもが、いかにも重々しい。
これは、この艦の能力の限界なのか?
それとも、及び腰な砲手や水兵たちの不安が、そうさせているのか)
フロレスは苦々しい思いで、美麗な横顔に光る碧眼を、艦尾楼の方へと走らせる。
その視線の先では、俯き加減の艦長が、キャビン前の高い後甲板で、落ち着き無く行きつ戻りつを繰り返していた。
ベルナルド艦長は40歳代中程の中肉中背のスペイン人だが、元々の相貌なのか、あるいは心労による窶(やつ)れのためなのか、小粒な黒目は深く窪んで、青ざめた額には深い皺が刻まれ、年齢よりも大分老け込んで見えた。
(英国艦隊を最も恐れているのは、ベルナルド艦長自身か――…)
そのように思い巡らせながら、フロレスは無意識のうちに唇を噛み締める。
確かに、まさか、このような状況下で、よりによって精鋭の英国艦隊と正面切って戦わねばならぬことになろうなどと、いかに艦長とて、一昨年、当地に着任した頃には夢にも思っていなかったに相違ない。
本来なら、英国は、今は北米の独立闘争との絡みで、北米の植民地軍やフランス軍との戦闘に忙しく、この時期にわざわざ南米に手を回すことなどあり得ぬはずではなかったのか?
恐らく、ベルナルド艦長の思惑はそのようなところにあったろうし、ましてや、数十年にわたってスペイン海軍に属してきた彼にとって、英国艦隊の恐ろしさは骨の髄まで染みているに相違ない。
(だが、どう足掻こうとも、英国艦隊がそこまで来ている現実からは、逃れようはないのだ――)
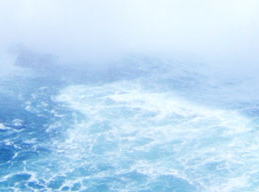
冷酷なほどに漠々と広がる海原を鋭い面差しで見やった後、フロレスは、再び砲撃訓練の方へと視線を戻した。
此度のスペイン艦隊の総指揮官たる当旗艦の艦長が、このような状態であることは、非常に心もとなく、また、危険でさえある。
とはいえ、スペイン本国であれば、艦長の替えなどいくらでもいようが、この新大陸では、軍艦を帆走させ、海戦を指揮できる人材など、とても限られているのだ。
今や、フロレスには、本来は海戦などに縁の無いはずの己が、この艦に配属された已(や)むに已まれぬ事情を、十分に察することができた。
(アレッチェ殿も、ベルナルド艦長が恐れをなしていることを、早々に察していたに相違あるまい……)
このフロレスは、風貌こそ、中世の騎士さながらの西洋的な雰囲気を多分にもっていたが、実際には、この植民地出身のスペイン人である。
この植民地で生まれたというだけで、差別と偏見に晒されてきた当地生まれの白人たち。
だが、このフロレスは、その卓抜した才気によって、この国の支配権を牛耳っていたスペイン渡来の白人たちを遥かに凌駕する出世を果たし、かつては最高司法院の議長まで任官したエリート高官である。
そしてまた、現在はスペイン陸軍に所属している彼は、此度のトゥパク・アマルの反乱幕開け以来、副王の篤い信任を得て、隣国ラ・プラタ副王領におけるスペイン軍総指揮官を務めてきた。
そのフロレスをラ・プラタ副王領から、急遽、呼び寄せ、いち早くこの旗艦に着任させたのが、フロレスの上官たるアレッチェであったのだ。

フロレスは、改めて、艦首から甲板、艦尾、そして、高々と聳えるマストへと視線を走らせる。
さすがにフロレスらしく、軍艦の帆走から戦術まで、海戦に必要なことは、その細部まで徹底的に頭に叩き込んではいたが、しかし、所詮は経験値の低い不慣れな艦上――容易には、見知らぬ異国の地にいるような違和感を拭い去ることはできなかった。
確かに、この時代の海戦は、敵艦の船体やマストを破壊して帆走能力を奪い、その後、切り込み隊を突撃させて降伏に追い込むのが一般的な戦い方ではあった。
従って、いわゆる「海兵隊長」として、陸上部隊の指揮官さながらに、艦上でも銃剣突撃を指揮できる人物が不可欠であった。
指揮官としての能力も、また、武術にも秀でていたフロレスが、その役目に抜擢されたとしても不思議はない。
だが、此度の場合、そうした海兵隊長としての権限に加えて、アレッチェは、このフロレスに旗艦艦長の補佐官としての権限――つまりは、ベルナルド艦長に次ぐ、スペイン艦隊そのものに対する大幅な指揮権限――を、与えていたのだった。
これまでは、いかなる異変や大事の前にも、その涼しげな目元を一縷も崩すことのなかった極めて沈着冷静なはずのフロレスの横顔にさえ、さすがに今は張り詰めた緊迫感が滲んでいる。
(本国スペインから当地に援軍に向かおうとするスペイン艦は、ヨーロッパ近海を離れる前に、悉(ことごと)く英国艦に撃退されていると聞く。
その上、昨夜のアレッチェ殿の伝令によれば、新大陸から帰還途上にあったスペイン艦も、此度の英国艦隊に敗れたと……)
無意識のうちに、フロレスの手は、艦首楼の手すりをきつく握り締めていた。
そこが、陽光に晒され、鉄板が焼け付くほどに熱くなっていることさえ忘れたままに。
(そのような英国艦隊を相手に、このようなスペイン艦隊で、どこまで渡り合えるものか。
もしや、アレッチェ殿は、陸に迫る英国艦隊の力を殺(そ)ぐために、我らを最初の捨て石にする気かもしれぬ――)

いつしか彼の碧い瞳は、風を受けて巨大な弧をなす大横帆に描かれた、堂々たる深紅の十字架を真っ直ぐに見上げていた。
(だが、どのような形であれ、ただでは決して終わらせん……!!)
かくして、スペイン側でも臨戦態勢が進んでいく中、その同じ遥か洋上には、悠然と進みくる英国艦隊の勇壮な艦影があった。
途上、新大陸よりスペイン本国へ帰還中のスペイン艦に襲撃を受けたが、さしたる損傷も受けず、また、幾つかの破損箇所も早々に修理が済んでいる。
敵の砲弾によって貫かれた帆の空隙も今はすっかり縫い合わされ、順風を受けて美しい弧を描くそれら純白の帆は、何事も無かったかのように、暮れなずむ緋色の空に映えていた。
此度の英国艦隊総指揮官ジョンストン提督の高いシルエットが、次第に水平線に下りゆく夕刻時の陽光に照らされ、彼の足元に長い影を引いている。
彼は後甲板の高みから降り来て中央甲板の舷側通路沿いに立ち、水兵たちが仕上げの訓練に奔走する姿を、その息遣いまで聞き取れるほどの近距離から鋭く見渡している。
その風貌は、厳粛で、精気に溢れ、威風堂々たる精鋭の英国艦隊を率いるにいかにも相応しげな品格と自信に満ちている。
それと共に、その深い碧眼には、寸分の油断も許さぬ、研ぎ澄まされた隙の無さが備わっていた。
白い折り返しの襟が覗く青い軍服姿の体躯もまた、隙無く引き締まり、それでいて見るからに強靭そうである。

その時、訓練を見渡す彼の視界を、何物かが一条の光の矢のごとく、高速で過(よぎ)っていった。
ジョンストンは、ハッと顔を上げる。
金髪が、西日を跳ね返してキラリと光った。
その彼の視界の中に、今度は、はっきりと一羽の鳥影が映った。
(あれは――!)
鋼のような翼をもつ鴎ほどの大きさをした灰褐色の鳥――海鳥とも渡り鳥とも見えるそのシルエットは、高々と聳えるメインマストの軸を旋回しながら、宙を切り裂くように滑空している。
ジョンストンは、素早い足取りで後甲板に戻ると、その高みから、鋭く口笛を一吹きした。
それを合図に、灰褐色の鳥は風を切って彼の元へと一直線に飛来し、差し出された提督の逞しい腕へと舞い降りた。
彼にとって見覚えのあるこの鳥は、まさしく、トゥパク・アマル陣営にいるアリスメンディの放った伝令鳥であった。
アリスメンディが上陸して以来、既に数回に渡って艦と陸とを往復している英国海軍の伝令鳥――。
素早い手つきで、鳥の足に括りつけられた布切れを解(ほど)くと、そこに書かれた文字に敏捷な視線を走らせる。
読み進むジョンストンの鋭利さを増しゆく横顔を、夕陽が緋色に染め上げていく。
(我が方が供与した武器は、インカ軍に渡ったか。
あのインディオの首魁の元に――!)
ひとしきり読み切ると、彼は厳然たる眼差しを水平線に向けた。
そこでは、今、まさに、黄金色の巨大な夕陽が大海原へと沈みゆくところであった。

こうして、刻一刻と戦の予兆をはらんで時が刻まれる中、インカ軍の状況はどうなっていたであろうか。
再び、舞台をインカ軍本隊、トゥパク・アマル陣営に戻そう。
早春の涼やかな風の吹き抜ける夕暮れ時の陣営では、トゥパク・アマルを中心に、彼の重側近及び十数名の隊長たちが広大な天幕に会(かい)し、詰めの軍議が進められていた。
中央に座すトゥパク・アマルの横には副官ディエゴの厳つい巨体があり、また、その周囲には、慧眼を光らせる老賢者ベルムデス、鷲のように鋭利な面持ちの護衛官ビルカパサ、そして、アンドレスやロレンソ、マルセラといった若き将たち、さらに、トゥパク・アマルの美しくも勇壮な妻ミカエラや三人の皇子たちの姿も見られた。
かつてであれば、この場には、参謀オルティゴーサの勇姿や重側近フランシスコの細いシルエットも見られたはずであり、また、かの褐色兵の将フィゲロアも座を共にしていたかもしれない――だが、もはや、彼らはこの世にはいなかった。
同様に、反乱が幕を開けてから、既に数万というインカ兵の命が奪われていた。
――しかし、この反乱を起こさずスペインの圧制に甘んじていれば、これまでがそうであったように、インカの民は、苦役と酷使にまみれ、やがて最後の一人まで死に果ててしまっていたかもしれないのだ。
押し寄せる苦渋と感傷を静かに押しやると、トゥパク・アマルは、総指揮官としての厳然たる面差しで、机上に広げた地勢図を指し示す。
トゥパク・アマルは、ディエゴに、そして、各隊長たちに、鋭利な視線を向けた。
ディエゴは、トゥパク・アマルを凌ぐほどに長身で、銃弾で打ち抜かれても心臓に届かぬのではと思わせるほどに強靭な岩のような巨躯をしている。
トゥパク・アマルが囚われていた間も、ビルカパサと共にスペイン軍と死闘を展開し続けてきた豪傑で、ただ座しているだけでも、場の空気を高揚させる「気」のようなものが漲っている。
そしてまた、そのようなディエゴと共に、今、トゥパク・アマルに力強い凛然たる視線を向けている隊長たちも、幾多の戦火を潜り抜けてきた筋金入りの精鋭たちであった。

トゥパク・アマルは、しなやかな褐色の指先を、インカ帝国の旧都クスコの輪郭に沿って滑らせた。
「ディエゴ、そなたは、牙城クスコの奪還に向けて兵を進めよ。
わたしの配下の軍勢、数万の多数をそなたにあずける。
此度の反乱で一度は苦渋の敗退を舐めているが、あの地の奪還は我らが祖先代々の悲願であると共に、植民地支配を瓦解せしむるためには、必ずや取り戻さねばならぬ場所」
そして、激情を秘めた美しい目を、各隊長たちの方にも走らせた。
「各隊長たちは、それぞれの要所に散り、打ち合わせ通り、時を合わせて一斉に蜂起せよ」
さらに、トゥパク・アマルは、アンドレスら若者たちの方にも素早い視線を馳せ、「ラ・プラタ副王領側については、アパサ殿の活躍はもとより、そなたたちの遠征も功を奏し、今はインカ側が優勢になっている」と言い添え、再び隊長たちに向いて続ける。
「この機に、ラ・プラタ副王領へも、さらに火の手を広げよ。
各地に散らばる同盟者たちとも、既に合意は取れている。
スペイン軍の戦力を、最大限に分散させるのだ」
ディエゴと隊長たちが、厳つい面差しに鋭利な眼光を閃かせて頷くのを確認すると、トゥパク・アマルは地勢図に視線を戻し、今度は海岸線を指し示した。
「わたしは、沿岸に布陣する陣営に降り、英国艦隊とスペイン艦隊の動きを見極め、海戦に備える。
アンドレス、そして、ロレンソ、マルセラ、そなたたちの部隊も、わたしと共に沿岸部へと降りてもらう」
「――!!」
アンドレスたち三人が共に息を呑み、大きく見開かれた若い瞳をトゥパク・アマルの方へと真っ直ぐ向けた。
武者震いをしている若者たちの面差しには、しかし同時に、いかに表に出すまいとしようとも、馴染みの無い海戦への戸惑いが滲み出す。

トゥパク・アマルはその目を細めて、三人に頷き、低く、沈着な声で言う。
「我々インカ側にとって、海戦など誰もが未経験だ。
そなたたちの躊躇(ためら)う気持ちは、よく分かる。
それに、海戦とはいえ、海上に出るだけが全てではない。
だが、いずれにしろ、此度の作戦では、かなりの体力と機敏さがいる。
そして、相当に卓越した剣の腕も必要だ。
そなたたちの部隊に多い若い兵士たちの力が欠かせぬ――アンドレス、ロレンソ、マルセラ、頼りにしているぞ」
そう言って、三人を力強く見つめるトゥパク・アマルに、アンドレスもロレンソも、そして、マルセラも、強い恍惚と緊迫感のない混ぜになった眼差しで、「はっ!!」と、恭順を示した。
「それから、アンドレス、そなたは、此度の海戦に臨む作戦では、わたしの副官に任ずる」
「――!」
光の矢が閃くようなトゥパク・アマルの鋭い眼差しを受けて、アンドレスは一気にその顔を紅潮させたが、己の任務を咀嚼するより前に、殆ど反射的に、「はい!!」と応えていた。
さらに、トゥパク・アマルは、その褐色の指先でサンガララ一帯の地勢図をなぞり、今度は、妻ミカエラ・バスティーダスに向いた。
女神が降臨しているがごとくに美麗な彼女の存在のためか、その周辺の空気ばかりは、まるで芳しく香っているかのようである。
他方、当のミカエラは、先刻から冷徹なほどに沈着な面差しで、夫を、そして、周囲の者たちを見守っていた。
その隙なく研ぎ澄まされた横顔からは、早々に己の役目を悟っている、と分かる。
トゥパク・アマルは、そのような妻にも、やはり総指揮官としての厳然たる口調のままに続けていく。
「ミカエラ、そなたには、この本陣を任せる。
各地への物資の補給を取り仕切り、わたしからの伝令を各地に伝え、また、そなたの判断で、この本陣を守るのだ。
かつて、そなたが、トゥンガスカの本陣を守っていたように――」
「わかりました」
ミカエラの雄々しくも艶やかな声音が、天幕の空気を煌かす。
そのような勇壮な妻に、トゥパク・アマルは熱を帯びた瞳で黙って頷き、それから、皇子たちにも向き直った。
「イポーリト、マリアノ、フェルナンド、そなたたちは、わたしのいない間、母上をしかと助けよ」
「はい!!
父上!!」
父母によく似た凛々しく美しい瞳を輝かせ、力強く頷く息子たちに、トゥパク・アマルも、「頼んだぞ」と微笑み、頷き返した。
そして、最後に、老賢者ベルムデスに深く礼を払う。
「ベルムデス殿、あなた様は、この本陣にて、ミカエラたちをお助け頂きたい。
この本陣は、各地に散った各部隊の要(かなめ)ともなる重要な司令塔。
あなた様が、ここにいてくだされば、非常に心強い」
「ありがたきお言葉。
トゥパク・アマル様の御心のままに」
老練で温厚な視線を伏せて深く恭順を示すベルムデスに、トゥパク・アマルも、真摯な眼差しで、今一度、深く礼を返した。

やがて、そろそろ会合も解散になろうかという頃、ディエゴが、その巨体をトゥパク・アマルの方へとやや前傾姿勢に乗り出した。
「トゥパク・アマル様、クスコの奪還は不可欠ですが、植民地支配体制の瓦解ともなると、あやつらの巣窟である首府リマを放置とはいきますまい」
「うむ」と、トゥパク・アマルも深く頷いた。
「確かに、かの地は、植民地支配を崩壊させるためには、必ずや陥落させねばならぬ場所。
だが、スペイン側の勢力が非常に強く、さすがに手を出しづらい――。
クリオーリョ(植民地生まれの白人)の者たちの協力が得られれば、ありがたいのだが……」
深刻げにそう言いながら、しかし、ふっと意味ありげに微笑した。
その表情の変化に、周囲の者たちは目を瞬かせ、にわかに身を乗り出す。
ディエゴが、その岩のような手で顎をさすった。
そして、「そのご様子だと、トゥパク・アマル様、何か、お心当たりがおありですな?」と、低く太い声で問う。
「うむ。
無いことも、無い、が――まだ、決定的ではない」
トゥパク・アマルは沈着な声でそう言うと、傍らにあった革細工の書類箱から、厚い書状の束を取り出した。
「それは?!」
側近や隊長たちが、いっそう身を乗り出す中、トゥパク・アマルは、その書状を隠し立て無く周囲の者たちにも閲覧を許しながら続けていく。
「これは、わたしと親交の深いクスコの酒場のマスターが、そこに集い来るクリオーリョの革命分子たちの様子を書き記し、折々にわたしの元に送り届けてくれたものだ。
書状にある通り、だいぶ前から、我々の戦にも関心を示している」
そう言って、「もう一押しで、我らの力となってくれるかもしれぬぞ」と、静かに微笑んだ。

そんなトゥパク・アマルの周りでは、皆、恍惚と息を詰めながら、夢中で書状を繰っている。
だが、不意に、ディエゴが厳(いかめ)しい面持ちで、再びトゥパク・アマルの方に、その巨大な体躯を乗り出した。
「しかし、トゥパク・アマル様――」
彼の太く強靭な指先が、書状の一部を、ぐっ、となぞる。
「この白人たちは、たとえ植民地体制が崩壊しようとも、あなた様がインカ皇帝として立たれることには、強い抵抗感を持っているようですが」
「そうようだな……」
ディエゴの言葉に、トゥパク・アマルが、やや前傾姿勢になっていたその身をゆるやかに正す。
瞬間、逞しく強靭な肩に巻きつけられた黒マントの黄金の留め金が、煌く閃光を放った。
彼は、美しい切れ長の目で、ディエゴを、そして、やはりディエゴと同じ眼差しで真剣に己に見入る周囲の者たちを、鋭くも、深く包み込むように見渡した。
「インカ帝国やインカ皇帝の復活を願うそなたたちの心は、とても嬉しく思っている。
かつて、この地に栄えた我らの帝国と我らの祖先のことを思えば、わたしとて、その思いが無いとは言えない。
だが、我々が此度の戦を起こしたのは、このインカの地に生きる全ての民を、非道なる植民地支配体制の鎖から解放するため――そのことが叶うならば、我らに、それ以上の望みは持てぬであろう。

時は移り、今や、この国には、白人や黒人などインカ族以外の民も多く住み、その者たちの子孫も、我らと同じくこの国を祖国としている。
この地に生きる全ての民が真に共存していくために、そして、新たな時代の中でこの国が独立国家として生き延びていくために、必要な変革は受け入れていかねばなるまい。
わたしの言いたきことを、そなたたちならば、分かってくれるね?」
そして、同じ頃、そのインカ軍陣営の上空には、鋭利な旋回を続ける一羽の鳥影があった。
山の端に沈んだ西日の残光で灰褐色の翼を紅く染め上げながら、地上の主(あるじ)の合図を待っている。
それは、アリスメンディが洋上のジョンストン提督に放ったのと同様に、提督からもアリスメンディに向けて放たれていた、もう一羽の伝令鳥。
その鳥の放つ甲高い声を聞き取ったアリスメンディは、己の天幕を抜け、周囲に敏捷な視線を走らせる。
常に隙無い監視の目を光らせているロレンソは、この時ばかりは、さすがにはずせぬという重要な軍議――つまりは、先刻の会合だが――に参席中で、今は傍にはいなかった。
ロレンソがどうしも付けぬ場合に代行している別のインカ兵が眼光をきかせてはいたが、執拗とも思えるほどに完璧なロレンソの監視に比べれば、かわすのは容易(たやす)かった。
アリスメンディは天幕近くの森の傍に何気ない足取りで歩みゆくと、木の葉に触れるような素振りで、スッと、さりげなく伝令鳥に合図を送る。
まもなく、鳥は、アリスメンディのすぐ傍の枝に舞い降りた。
だが、周囲の目には、恐らく、たまたま野鳥が羽を休めに木にとまった、としか見えなかったであろう。
彼は、そのまま鳥には目もくれず、ただ木々の葉を吟味するかのような手つきで、手探りのまま伝令鳥の足に結ばれていた布切れをスルリと解(ほど)き取った。
そして、そのまま、瞳だけを僅かに動かし、布切れの方へと視線を走らせる。
アリスメンディは冷ややかなほど淡々たる横顔で、そこに記された伝令文を一瞥(いちべつ)すると、何事もなかったかのように、「護衛」のインカ兵の前を通り過ぎていった。
僧衣の衣擦れの音だけが、草の上に静かな痕跡を残していく。
常と変わらぬ足取りで、しかし、次第に己の天幕を離れ、陣営中心部へと向かう小道を歩みだしたアリスメンディを、インカ兵が慌てて追いかけた。
「アリスメンディ様、どちらに行かれるのです?!」
アリスメンディは、風の香りをかぐようにして、茜色から次第に宵闇の藍色に移りゆく上空を振り仰いだ。

「いや、なに。
風が心地よい。
少し、その辺りを歩いてこようかと思ってね」
「では、わたしもお供いたします!!」
真剣な面持ちで詰めるようにしてくる兵に、アリスメンディは、「好きにするが良い」と、やや苦笑しながら声だけで応じ、空を見上げたまま歩み進んでいく。
その視線の遥か先では、先刻の伝令鳥が、星の瞬きはじめた天頂を自在に舞っていた。
一方、その頃、トゥパク・アマルたちは軍議を終え、それぞれの任務へと戻っていくところであった。
ビルカパサに護衛されながら陣営を歩み行くトゥパク・アマルの脇には、次の任務のために、この時は偶然にも、同じ方向へと戻り行くアンドレスの姿があった。
白人たちの中にも革命分子が生まれている――先刻のトゥパク・アマルの話と、そして、今しがた目にした書状の内容が、アンドレスの心の中に鮮烈に焼きついていた。
そして、同時に、以前、アリスメンディが己に話してくれた北米での独立闘争のことが脳裏に強く蘇ってもいた。
彼は思い切ったように、トゥパク・アマルの方へと顔を上げる。
「あの、トゥパク・アマル様!」
「何だね?」
「いえ、あの…トゥパク・アマル様は、やはり世界情勢を視野に入れて、此度の英国艦隊を動かそうと思われたのですよね?
あの北米での独立闘争との絡みで、英国がフランスや北米の植民地軍との戦いで手薄になっていることを見越した上で。
だから、今は英国が全力では当地の攻略に乗り出せないと見込んで、このタイミングで呼び寄せた」
予想だにしなかったアンドレスの言葉に、トゥパク・アマルは、足早に歩みつつも、相手の顔を振り返って凝視した。
「何故、そのように思った?」
「いえ…、俺が気付いたのではなく、アリスメンディ殿がそのように仰っていたのです」
「アリスメンディ殿が――。
そうか」
トゥパク・アマルは、僅かに目を細める。
そして、再び前方に向き直った。
「それで?
アリスメンディ殿の話を聞いて、そなたはどう思ったのかね?」
周囲の陣営内の様子に隙無く視線を馳せながら敏捷な足取りを変えぬトゥパク・アマルに、アンドレスも懸命に追いつきながら応える。
「同じように植民地からの独立!
しかも、向こうでは、植民地軍が優勢に戦を展開していると聞きました。
ならば、俺たちも、北米の独立闘争から学べるところがあるのではないかと!!」
少し離れたところで護衛をしながら二人の会話を見守っていたビルカパサは、聞こえようによっては、トゥパク・アマルのこれまでの戦略を批判するものともなりかねぬアンドレスの発言に、思わずヒヤリと肝を冷やす。

しかし、単刀直入なアンドレスの言葉に、トゥパク・アマルは、むしろ微笑した。
それから、やや歩む速度を緩めながら、沈着な声音で語りはじめる。
「確かに、学べるところは、学ぶにこしたことはあるまい。
ただ、北米の植民地軍の兵士、つまりは民兵たちは、あの地の純粋な先住民ではなく、渡来した白人の子孫や混血児だった。
そのことによる我らとの大きな違いは、元々、彼らは銃を身近に保有し、そして、それを使い慣れていたということだ」
「え…?!
戦になる前から、銃を使い慣れていたのですか?!」
「そうだ。
彼らは、普段の生活の中で、銃による狩猟を盛んに行ってきた。
敏捷な獣たちを撃ち慣れてきた彼らの正確な射撃が、そのまま戦に役立っている。
我らインカ族のように、銃を持つことを堅く禁じられ、銃の製造過程すら見ることの許されなかった民族とは、そこが大きく違う」
「――はい」
アンドレスは、無意識に地に視線を落とした。
沈んでしまったように見える相手に視線を走らせながら、トゥパク・アマルは続けていく。
「そう肩を落とすことはない。
銃器の慣れの違いはあろうが、もっと重要なことは、北米の民兵たちは、非常に士気が高かったということ――それが、あそこまでの戦果を生む原動力ともなったのだ。
北米の民兵たちは、我が義勇兵たちと同様に隊列を組む方法の一つすら知らなかったが、にもかかわらず、よく訓練された正規の英国軍を相手に戦った。
それでいながら、あれほどの戦果を上げたのは、有能な指揮官がいたこともあろうが、何より民兵たちが強い独立意欲に燃えていたために他ならぬ。
士気ならば我らの民の間にもあろうし、それを、さらに高めることは我らにも可能なはずだ」
アンドレスは再び顔を上げて、トゥパク・アマルを見上げ、決然と頷いた。
「はい!!」
他方、トゥパク・アマルは、吹き付ける宵闇の強風を切って、その精悍な横顔を真っ直ぐ前方へと向けた。
「そなたの言う通り、我らが北米の独立闘争から学べることは、決して少なくない。
殊に、現地に生まれた白人たちの力…――その潜在力、侮れぬ」
そのような会話をトゥパク・アマルとアンドレスが交わすうちにも、次第に夜の帳が降りゆく陣営の随所では、松明の炎が夜空を照らしはじめている。
その時、それら松明の灯りを避けるかのように、やや奥まった木々の陰に、不意に漆黒の僧衣姿を認めて、トゥパク・アマルとアンドレスは同時にそちらを注視した。

他方、そんな二人の姿に向かって、アリスメンディは深い闇の向こうから丁重に礼を払うと、その鋭い目元に僅かな微笑を浮かべた。
次の瞬間、トゥパク・アマルとアンドレスを背後に匿(かくま)うようにして、いちはやくビルカパサの厳つい体躯が二人の前面に飛び出した。
「アリスメンディ様、このようなところで何を?」
礼を失しないよう振る舞いながらも、野性的なビルカパサの眼光は鋭い。
「いえ、ただ夜風に当たっていたのです。
ですが、今、トゥパク・アマル殿のお姿を偶然お見かけして、そう言えば、お話ししたいことがあったと思い至り…、こうして足を止めておりました」
そう言って、陰になった横顔を己の方へと向けるアリスメンディの方へ、トゥパク・アマルも一歩出て、しなやかな手つきで己の前にいるビルカパサを脇へと促した。
ビルカパサは構えを変えぬまま、しかし、やむなく礼を払って脇に退く。
「アリスメンディ殿、本当に、今宵はよい風ですね」と、穏やかに語るトゥパク・アマルの漆黒の長髪は風の中でゆるやかに舞い、月明かりの粒子と戯れながら白く輝いている。
「このような風が英国艦隊にも吹いていれば、さぞ、航海は順調でありましょう」
そう微笑みながら続けるトゥパク・アマルの前で、アリスメンディも微笑したまま、ゆっくりと、深く、頷いた。
「恐らく、英国艦隊の航海は、トゥパク・アマル殿の仰せの通りでありましょう」
含みを持たせて語らう二人の視線が、静かに、しかし、激しく、交錯する。
やがて、再び、アリスメンディが口を開いた。
「実は、ジョンストン提督から、トゥパク・アマル殿に重要な託(ことづ)けがございまして」
「託け?」
「はい。
お人払いを願えますか?」
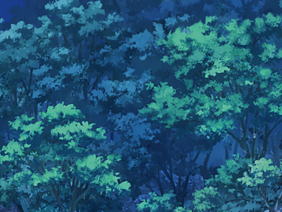
トゥパク・アマルは、僅かの間、僧の方へとうかがうように視線を馳せていたが、やがて周囲の兵たちに「下がっていなさい」と低く言う。
しかし、頑として動こうとしないアンドレスとビルカパサには、アリスメンディも「お二方は、構いません」と応えた。
改めて、夜風の中でアリスメンディに向きながら、トゥパク・アマルが問いかける。
「それで、提督からの託けとは?」
「はい」
アリスメンディは恭しく礼を払って、眼光の閃く漆黒の瞳を見開いた。
「ジョンストン提督は、と申しますか、英国は、あなたと正式な同盟を結びたいと望んでおります。
同盟を結べば、英国軍は当地からスペイン軍を撃退し、スペイン植民地下から独立するあなた方を全面的に支援すると。
もちろん――あなた方が独立を達成した暁には、英国側は、それ相応の優遇を受けることを契約した上でのことですが」
暫しの沈黙の後、表情を動かさぬトゥパク・アマルの声が、「それ相応の優遇ですか…」と、ただ低く響いた。
そして、やや皮相な声で続ける。
「それは、ずいぶん高くつきそうですね」
「トゥパク・アマル殿……」
鋭い目線で探るように見据えるアリスメンディの周囲では、アンドレスとビルカパサが大きく固唾を呑み、表情の見えぬトゥパク・アマルの横顔を凝視している。
4人の頭上では、黒々とした木々の太い幹が、夜風の中でザワザワと不規則に揺れている。
トゥパク・アマルの纏うマントもまた、風の中で大きく翻った。

「アリスメンディ殿、せっかくのお話ではありますが、我々は英国と同盟を結ぶ気持ちは持ってはおりません。
『同盟』という言葉は美しいが、その表面ではどのように仰ろうとも、その内実は、提督を含め英国の方々は、我ら「未開のインディオ」を対等に見てはおりますまい。
そのような両者の間で、まっとうな同盟関係が成立するとは思えません。
せっかくの独立も、英国の属国になるためのそれでは、意味がないのです」
「トゥパク・アマル殿――!」
急遽、激しく緊迫した空気に、いよいよアリスメンディが牙を剥くのではないかと、ビルカパサが腰の剣に手をかけ、すかさず身構えた。
さすがのアンドレスも、激しい困惑の表情ながら、対峙しているトゥパク・アマルと僧の間に踏み込まんばかりに、大きく身を乗り出す。
しかし、それらを、トゥパク・アマルの腕が、瞬時に鋭く制した。
暫し、張り詰めた沈黙が流れる。
が、やがて、アリスメンディが、その非常に険しくなっていた形相を、ふっと苦笑させた。
「トゥパク・アマル殿、あなたは、そう仰ると思っておりました。
まあ、実際、同盟の対価は、たいそう高くつくことでしょうからな」
「アリスメンディ殿」
能面のごとく表情の見えなかったトゥパク・アマルの横顔に、僅かに人肌らしい色が差した。
それから、次第に、案ずる気配に変わる。
「ですが、アリスメンディ殿、このような回答では、あなたの御身に危険が及びましょうか?」

「いや、なに、わたしのことなど、どうにでもなる」
そう囁くアリスメンディの微苦笑を帯びた面差しは、この期に至っても、なお、その裏が読めない。
ビルカパサも、そして、アンドレスやトゥパク・アマルでさえも、無意識にアリスメンディの表情に釘付けられている。
だが、そのような彼らをよそに、アリスメンディは、淡々たる声音で続けていく。
「トゥパク・アマル殿、我らの持参した武器も無事にあなたの御手に渡った今、ましてや同盟も成立せぬともなれば、あとは、三国三つ巴(みつどもえ)の戦火に突入するのみ。
そうなれば、このような丸腰の僧など、もはや、何の役にも立ちはいたしません。
あなたがたインカ軍と英国艦隊との橋渡しをするわたしの役目は、そろそろ一区切りでございましょう」
「アリスメンディ殿……」
月光の中で、トゥパク・アマルの長身なシルエットが、アリスメンディの方へと、さらに一歩を踏み出した。
「昔も、そして、今も、我らインカに対するあなたの甚大なお力添えには、感謝の思いが尽きません。
あなたさえよろしければ、我らの元に、本当にお戻りになってはくださいませんか?」
深い礼を込めた真に誠意溢れるトゥパク・アマルの声と眼差しに、アリスメンディも、今一度、丁寧に礼を払う。
それから、ゆっくりと、鋭利さのいや増した横顔を上げた。
「トゥパク・アマル殿、あなたのお気持ちは嬉しい。
ならば――最後に、ひとつお願いがございます。
これは、此度の英国艦隊とは全く関係のない、わたし個人のお願いでございます」

「アリスメンディ殿個人の願いと申しますか?
わたしとて、あなたの意に添いたいが、一体、何を?
まずは、その内容を教えては頂けませんか?」
トゥパク・アマルの真摯な声音が、低く響きながら、夜風に運ばれていく。
黒衣の僧は、青白い月明かりの中に、炯眼の光る刃物のごとく鋭利な輪郭を浮かび上がらせたまま、トゥパク・アマルを見つめ、それから、アンドレスにも、暫しの間、じっと視線を注いだ。
まるで、そこに、遠い誰かの姿をうつしとるかのように――…。
一方、トゥパク・アマルの少し後方でアンドレスは澄んだ大きな瞳を揺らしながら、祈るような、深く案ずるような眼差しで、アリスメンディを見守っている。
やがて、僧は、トゥパク・アマルへと視線を戻した。
「トゥパク・アマル殿、あなたは、先日、わたしに真の望みは何かと聞いてくださった。
インカの民の解放とお応えしたその思いに、偽りはございません。
そして、その為にも、わたしなりに決着を着けねばならぬことがある。
行かねばならぬ場所があるのです」
ところで、この頃、インカ帝国旧都クスコの様相はどうなっていたであろうか。
クスコの地は、トゥパク・アマルが陣を張るサンガララの地から、そう遠くはない場所である。
かくして、インカ軍、スペイン軍、英国軍、それぞれの思惑が蠢く中、スペイン側の重要人物アレッチェと並ぶ、否、見方によっては、いっそう重要な人物であろうモスコーソ司祭もまた、その胃袋を激しく煮え滾(たぎ)らせていた。
モスコーソ司祭――クスコに本拠地を置き、この国のカトリック教会の頂点に立つ最高位の司祭である。
彼は、単に宗教的な意味合いで高位に君臨する存在というだけでなく、この植民地統治における絶大な発言力を有する政治的権力者でもあった。

そして、その彼は、今、サント・ドミンゴ教会の一角に設けられた豪華な司祭執務室で、苛立たしげに部屋の隅から隅まで、幾度となく行きつ戻りつを繰り返している。
ちなみに、このサント・ドミンゴ教会は、かつてインカ帝国時代に政治と宗教の中枢であった「太陽神殿(コリカンチャ)」のあった場所に建造されていた。
インカ帝国時代、この神殿には神々に捧げる黄金が満ち、燦然と光り輝いていたと言われる。
かつて、神殿内部には黄金の祭壇が供えられ、そこに黄金の太陽像が祀られていた。
そして、神殿の壁には黄金が貼られ、さらには、屋根にも黄金の茅が葺かれていた。
しかし、スペインの侵略によって太陽神殿は取り壊され、その上にこのサント・ドミンゴ教会が建てられたのだった。
インカの人々が神聖な黄金で埋め尽くしていた太陽神殿――それほどに重要な聖なる場所であったが故に、侵略者たちは、敢えてその上に自分たちの教会を建設することで、精神的にもインカ帝国を征服したことの象徴としたのである。
ただし、神殿の石積土台部はあまりに堅固で、スペイン人には取り壊すことができず、結局、その土台の上にコロニアル風の教会が建造されたのだが。
ともかくも、今、その教会の一室で、モスコーソ司祭は、この反乱がはじまってから蓄積し続けてきた心労もあるのか、いっそう肥満の増した恰幅の良すぎる全身を揺らしながら、落ち着き無く、ぐるぐると部屋中を徘徊し続けている。
宝石を散りばめた巨大な十字架が胸元で揺れながら、燭台の炎を反射して、ぬめるように光っている。

やがて、半ば放心して足を止めると、今度は足元の床を乱暴にギリリと踏み締めた。
まるで、スペイン教会の下敷きにされながらも、不動の堅固さで現存している太陽神殿土台部を踏みにじるがごとくに。
「おのれ――トゥパク・アマルめ……。
あの悪魔は、ついに乱心しおったのじゃ!!
英国艦隊の襲来は、あの悪魔の仕業に相違あるまいに……!」
肥満に膨れ上がった額に青筋を立てながら、血走った目をむき、ギリギリと切歯扼腕する姿は常軌を逸している。
かくも凄まじい形相で、執拗に床を踏みつけながら、司祭は独りで呻き声を放ち続ける。
「トゥパク・アマル、あの者は、我がスペイン軍を叩き潰すためなら、いかような手段にでも出ようとの魂胆なのじゃ。
おお…なんと、なんと恐ろしい……!!」
司祭は、いよいよ己の胸を苦しげに掻き毟りながら、よろけるように傍の柱に縋りついた。

「しかも…しかも、あのアリスメンディが、英国艦隊に乗り込んでおるなどと!!
国外追放までされたはずのあの者が…再び、この地に…!
なんたる…なんたることぞ……。
英国軍と共に我らをこの国から叩き出し、余に…余に取って変わって、この国のキリスト教会の最高位につこうと狙っておるのじゃ――!!」
殆ど妄想とも思えるほどの念に悶えながらも、モスコーソ司祭は、今にも卒倒しそうな巨体を、それでも懸命に柱に縋りついたまま支えている。
そして、胸の巨大な十字架を激しく鷲づかみにすると、荒い息の下で、恐るべき憎悪と執念に燃え上がる眼をいよいよ炯々と光らせた。
「おのれ…――トゥパク・アマル…アリスメンディ!!
これほどのことをしでかしおって、その結果がどうなるのか、必ずや、己らの身をもって思い知る時が来るであろう……!!」


